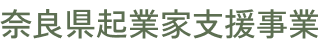インタビュー
2025/2/27
「奈良県生駒市にエシカルな暮らしのモデルルームをつくる」atelier 稲穂(奈良県起業家支援事業 採択者インタビュー/VOL.1)

| atelier 稲穂 奈良県生駒市でエシカルな暮らしを営む木下さん。2024年、自宅の隣に暮らしのモデルルーム「atelier 稲穂」を立ち上げることに。起業家支援事業費補助金200万円を、工事費と電気釜の購入に活用しました。 |
「自然に寄り添うエシカルな暮らしをひらき、広げたかったんです」
近鉄生駒駅から歩いて5分。隣に川が流れる自然豊かな土地で畑を営み、犬、猫、鶏とともに暮らす木下さん。

奈良市内に勤め、26年にわたって建築設計のコーディネートをしてきました。育児がひと段落した2023年に会社を退職。翌年、エシカルな暮らしを広げるアトリエをはじめます。
エシカルは英語で「倫理的」「道徳的」を意味し、環境や社会に配慮した選択をすること。こう説明すると難しそうですが、木下さんの自宅を訪ねると、こんな風景が広がっていました。

「わたしはとにかく動物が好き。命あるもの全て好きなんです」
自身で設計デザインを手がけた自宅は断熱性にこだわり抜き、自然エネルギーを有効活用しています。この日の外気は5℃と冷え込みましたが、室内はぽかぽかと心地よい。
「朝つけた薪ストーブの温もりが、火を落としたあとも続いています。もちろん薪は自分で集めたもの。食卓に並ぶ野菜や卵は、裏の畑で採れたものです」
お金の重力を軽くしつつ、自然のめぐみを受けとりながら生きる暮らしがありました。
どんな事業をしていますか?

つどう、はなす、つくる、たべる、まなぶ。いろいろなアプローチで、エシカルな暮らしの発信事業を行う「atelier 稲穂」をオープンした木下さん。陶芸や発酵料理といった自主企画講座を中心に、ワークショップや教室を開催していく予定です。

エシカルな暮らしをおすそ分けするモデルルームともいえるこの空間を、なぜはじめたのでしょうか。
「わたしは家に人を招くのが好きなんですが、コンポストや薪ストーブのある暮らしに触れてもらうことで、人の価値観が変わる瞬間に何度も立ち合ってきました。暮らしは、ちょっとした工夫で変えられる。そのことを五感で受けとれる空間がつくれたら、エシカルな暮らしがじわじわ広がっていく予感がしました」
atelier 稲穂で開催した「蔓(つる)で編む鳥かごワークショップ」では、こんな光景に出会いました。

「ワークショップが終わったあと、アトリエのまわりを歩いて、葛つるを見渡しながら『あれがこんなすてきなものに変わっていくんですね』とうれしそうに話してくれました。かご編みを体験することで『発酵料理もつくってみたい』『コンポストをはじめようかな』『うちでも鶏飼えるかな』と世界が広がっていく人もいます。自分の手を動かすことで、商品として売られているものも誰かがつくっていることに気づく。そうやって、世界の見え方が変わっていくんですね」
どうして応募したんですか?
「自分の納得のいく形にしたかったんです」

「建築資材が高騰していることもあり、予算は想像を超えていました。でも、なんでもかんでもコストとして切り詰めてしまうのではなく、エシカルな暮らしを体感してもらう空間をめざし、建築コーディネーターとして、大切にしたいことをこだわり抜きました」
電気窯への電気配線を地中化したい。
「内見時、この土地は“宝の山だ”と思いました。敷地内には、さくらやもみじの木が植えられていたんです。アトリエを訪れた人に四季折々の彩りを楽しんでもらえるよう、電柱や電線は見えないようにしたかったんです。それには追加の予算が必要でした」
そして外壁は新建材ではなく、杉板をよろい張りにしたい。

すでに工事は6月中旬から着工していました。資金の一部は融資で補う計画でしたが、いろいろな制度を調べるなかで、奈良県起業家支援事業を知りました。7月に行われた説明会に参加し、起業家支援事業に応募しました。
支援事業をどう活用しましたか?

採択後、200万円の起業家支援事業費補助金を「工事費の一部と電気窯の購入」にあてました。陶芸はatelier 稲穂を立ち上げる上で、欠かせない要素でした。
「もともと料理が好きで、自然とうつわにも興味をもちました。売られているうつわを眺めては『質感はいいけれど、形がな』『もう少し軽かったらな』という違和感を感じるなか、自分のつくった器に、バーンと料理を盛りつけてみたくなったんです」
2023年12月に会社を退職した木下さんは、翌年の正月に生駒市在住の人気陶芸家・高島大樹さんと出会いました。
「『ぼくも力になるから、アトリエで陶芸教室をやってみては?』と高島さんから声をかけていただきました。atelier 稲穂が動き出好きっかけの一つになりました」
伴走支援はどうでしたか?
伴走支援を担当するのは、中小企業診断士で、日頃から経営者の経営相談をしている梶さん。

陶芸や発酵料理といった自主企画講座の実施を中心に考えていたatelier 稲穂ですが、2024年11月に内覧会をひらいたところ、定員の3倍にあたる30組が訪れました。そして、レンタルスペースとして利用したい人が多いことに気づきました。その想像以上の反響に、2人はマーケティング戦略を立て直しました。
長年会社勤めをしてきた木下さんにとって、個人事業主としての経営は未知の世界でした。そこで梶さんは、水先案内人のような頼もしい存在となっていきました。
ニーズがあることは明らかになったけれど、atelier 稲穂をレンタルスペースとして運用したいわけではなかった木下さん。「エシカルな暮らしを広げる」というコンセプトに立ちかえり、相手の活動に共感した場合だけ活用してもらうことを決めました。これまでに、しめ縄ワークショップ、パーマカルチャーをテーマにした映画上映会などを開催。奈良県内だけでなく、大阪や兵庫からも人が訪れ、じわじわと「エシカルな暮らし」の輪は広がりつつあります。
また自分1人で事業を進めていくと、つい抜けがちなセキュリティへの気配り。この点も梶さんは抜かりありませんでした。不特定多数の人が訪れるのではなく、顔の見える人たちが集うコミュニティをめざすことを提案されました。お互いが安心して関わり続けられるよう、会員規約の整備や入会金の設定、免許証等での身元確認なども行うように。そして、電子決済の採用により、現金を扱わないで済むように。
今後の事業展開、聞かせてください。
2025年の目標は、陶芸教室をはじめることだという木下さん。陶芸家の高島さんによる指導を受けつつ、現在は作陶の腕を磨いているところでした。

同時に、atelier 稲穂にはいろいろな声が寄せられます。
「発酵料理教室をひらいてほしい」「結婚式をしたい」「スタジオとして借りたい」といったように。
「想いが膨らんでいく場なのでしょうね。たしかに、できることはいろいろあります。求められていることもいろいろあります。もしかしたら、建築コーディネートの相談をいただくこともあるかもしれません」
ビジネスにおいて、ニーズに応えていくことは基本といえます。けれども、ニーズありきで動いては、自分を見失ってしまうかもしれません。だからこそ「エシカルな暮らし」に立ち返ります。
「子どもや孫の世代まで、わたしたちがどう豊かに生きるか。まずはわたしが一番楽しむことから考えてみたい。今のわたしは、自分の足どりで進んでみたいんです」

(編集 大越はじめ 撮影 奥田峻史/toi編集舎)