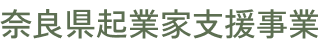インタビュー
2025/3/14
「奈良県広陵町から若手医療従事者が働きたくなる職場を育む」リライブ訪問看護ステーション(奈良県起業家支援事業 採択者インタビューVOL.2)

| リライブ訪問看護ステーション 2024年、奈良県広陵町に新たな訪問看護ステーションが立ち上がりました。メンバーは、看護師3名と事務員1名。起業家支援事業費補助金200万円を、医療器具とパソコンの購入に活用しました。 |
「20-30代の訪問看護師を増やしたいんです」
広陵町にある商業ビルの2階。ここに、リライブ訪問看護ステーションのオフィスがあります。ワークチェアに座り、タブレットやパソコンをひろげて打ち合わせる姿は、まるで医療ベンチャーのよう。
リライブ訪問看護ステーションを運営する株式会社First Class。代表を務めるのが、橿原市出身の看護師・西田さんです。
「病院で働くなかで『看護師は命を預かる大切な仕事だ』と日々感じ、患者さんと触れ合うなかで『看護師を一生の仕事にしたい』と思うようになりました」

退院を幾度となく見送るうち「退院の先を見てみたい」と、訪問看護の世界へ飛び込んだ西田さん。
訪問看護では、バイタルチェックや全身状態の観察はもちろんのこと、服薬チェックやお風呂の介助、点滴などの医療処置、そして最期を看取ることもあります。
「訪問看護で利用者さんの自宅を訪れると、笑顔を見られる瞬間が一番うれしいんです。一対一で接することができるから、お互いの信頼関係も生まれやすいことに気づきました」
どんな事業をしていますか?
2024年10月、西田さんは3人の仲間とリライブ訪問看護ステーションを開設しました。
2年に及ぶ起業準備をともに進めてきたのが、幼馴染の平(ひら)さんです。二人は、大学時代から「いつか起業しよう」と話す仲でした。

西田さんは、二つの視点から訪問看護に着目していました。一つ目は、日本の“最期を迎える場所”を多様にしたいという想い。「現在は、実に多くの方が病院をはじめとする施設で亡くなられています。人生の最期を自宅で迎えたいと希望される人が多いなか、在宅で最期を迎える人は10%台に留まっているんです」
二つ目は、20-30代の訪問看護師を増やしたいという想い。現場を支える訪問看護師の約70%は40代以上という調査も。西田さんと同世代の看護師の多くは、病院勤務でした。訪問看護の需要が高まる一方、訪問看護師数は不足していると言われています。
「それならば、ぼくらが、奈良県で20-30代が働きたくなる訪問看護の職場をつくればよいのでは?」
そのまっすぐな思いは、同世代の看護師を動かします。立ち上げのタイミングで仲間入りしたのが、看護師の小原さんと南さんでした。

「20-30代の看護師にとって、病院以外の選択肢が増えていくといいな」と話すのは、メガネをかけた南さん。
「病院で働いていると、退院後の様子が見えません。中なかには退院してもすぐ再入院する方もいます。退院後、家でどう暮らしているのだろうと気になっていました」
小原さんは、リライブの採用が決まり入社するまでの間、埼玉県の訪問看護ステーションへ。「少しでも力になれるように」と実務経験を積んできました。
「同じ看護師の仕事でも、病院看護と訪問看護では大きく変わります。たとえば、病院では在庫を常備している医療物品。利用者さんの自宅では切らしていることもあります。利用者さんの医療費負担も考えて、代用品で対応することもあります」
広陵町には、専門的医療を行う大病院がありません。そのためリライブは、往診医を含めた「多職種連携による地域医療」をめざしています。
その第一歩はすでにはじまっています。往診医との提携、利用者を担当し地域を支える介護支援専門員との地域連携。2025年には、理学療法士と言語聴覚士による訪問も開始しました。

どうして応募したんですか?
2024年に入り、奈良県起業家支援事業の制度を教えてくれたのは、広陵町で地域のために活躍する知人でした。
「こつこつと事業計画書の準備を進めているタイミングでした。事業計画をもとに、起業家支援事業の書類作成も進めました」
書類審査通過後のプレゼン審査では「自分たちの強みは若さにあります」とアピール。資料に記載されているデータにより、事業の実現性を裏付けることができました。
支援事業をどう活用しましたか?

訪問看護事業には、経費の大部分を人件費が占めるという特徴があります。200万円の起業家支援事業費補助金は人件費、そして医療機器やパソコン購入に活用しました。
その際に意識したのが、ICTの活用です。限られた人的リソースを最大限に活かせるよう、訪問看護での医療処置は電子カルテに記録することで、業務効率化を図り、より行き届いたケアをめざしました。
伴走支援はどうでしたか?

訪問看護ステーションは増加傾向にあります。競争が高まるなか、まずは認知を広げることが必要でした。
リライブ訪問看護ステーションはどんなことができるのか。地域連携のためにいろいろな方々にあいさつ回りを行い、開設初月から依頼をいただくように。事務を担当する平さんのバックアップもあり、より多くの時間を看護業務にあてられるようになり、こまめな訪問を必要とする終末期の利用者さんの看取りも叶えました。

地域貢献にも力を入れています。
「一番大事にしたいことですね。スーパーマーケットで無料の健康相談を開催し、まちのイベントに参加して子ども向けの仕事体験も行いました」
起業してから常につきまとうのが、お金の不安です。医療保険や介護保険の制度上、入金に時間がかかることもあり、キャッシュフローの見直しを迫られる場面も。そこで、伴走支援の面談では、35歳以下の新規創業向けの金利ゼロ融資制度を紹介されました。
また訪問看護ステーションの立ち上げにあたっては、看護業務にくわえて経営、財務、人事、そして広報まで、幅広い業務が待ち受けていました。
起業してからの2ヶ月間は、つい力技で対応することも多かったといいます。伴走支援の面談で受けた次のアドバイスが、業務改善へとつながりました。
「困りごとを誰でも解決できる『業務の仕組み化』に取り組みましょう」
ここで西田さんに聞いてみます。伴走支援について、追加の希望はありますか?
「これ以上の希望はありません。ぼくらは、自分たちの地力をつけたいと思っています。行けるところまで自分たちで行ってみたいんです。そういうスタンスを否定することなく、『気軽に相談してくださいね』と声をかけてもらえたことが、めちゃくちゃ心強くて!」
今後の事業展開、聞かせてください。

「まずは経営の安定をめざしたいです。そのためにもより多くの方に利用してもらいたい。その先には、4人目の看護師の採用も見据えています。現在は女性が2名、男性が1名なので、できれば数少ない男性看護師をもう1人採用したいんです」
「そして、20-30代の医療従事者の働き方の選択肢を増やしていきたい。中長期的には、奈良県内での店舗展開ができれば理想的です」
思いがあるからこそ、仲間が集まる。加えて、戦略性や行動力も持ち合わせている。そんな4人の取り組みは、この先も広がっていく予感がします。
(編集 大越はじめ 撮影 奥田峻史/toi編集舎)